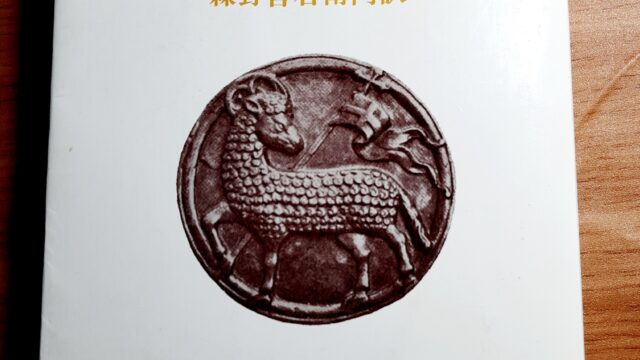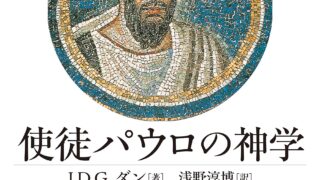あらすじ
本書「初めに、神が~創造を貫き、堕落を凌ぐ神の愛~」は、遠藤嘉信先生の創世記シリーズの1冊であり、創世記1章1節~3章20節天地創造から、人の堕落、救いの預言の出来事について語られている。本書は、「初めに神が天と地を創造した」という創世記1章1節の箇所の説明から始まる。
神がこの世界を創造したという言葉は、この世界の全てに偶然はなく、神の知恵に満ちた摂理の中にあることを指し、造られたすべてのものに生きる目的と意味を与える。
神は、この世界を6日という期間で創造され、最後に人間を造られた。
神は人間を造る時、「さあ、人を造ろう」と語り、神の大きな愛情と熱心さをその言葉に込めた。そして、人間を造られた時、神は他の被造物と一線を画し、「それは、非常に良かった」と語られた。
神は、人間を地のちりで造られたと同時に、そこに神ご自身の命の息を吹き込まれた。その命の息は、神の愛の息吹であり、神の事を知る知識が含まれている。人間の尊厳はまさにそこにあり、人間は被造物の中で唯一自由を与えられた存在であった。
神は世界を人間のために用意され、人間はその世界を生きるために造られた。そして、その中に生かされた特別な人間には、他の被造物にはない大きな役割が与えられた。それは、この世界を神の代表者として、管理することだった。
しかし、人間は一人では不十分な存在だった。人間には必ず助け手が必要だった。男は、あらゆる動物を見てきたが、満足するような相手は見つからなかった。
男は、自分にふさわしい存在が現れることを期待するようになった。そこで神は、男のあばらから骨を取り、女を造られた。男にとって、その造られた女は、まさにこれ以上のないパートナーであった。そして、二人は裸であることを恥ずかしいとは思っていなかった。なぜなら、すべてが良い状態であったからである。
裸であること自体を受け入れ、それ以上の評価もそれ以下の評価も下す必要がなかった。それ自体が素晴らしかった。
しかし、ある時サタンは蛇を遣わし、人間を誘惑した。この蛇は非常に狡猾であり、人間は見事にその誘惑に負けた。
その結果人間は、罪を犯し、裸であることを知り、それを隠したのである。裸を隠したという出来事は、裸であることが恥ずかしいという意味ではなく、罪を犯したことを認識し、神からその罪を隠そうとした行動である。自らの罪を隠し、何も処理しないままでいることは、本当の幸せではない。神の前に罪を告白し、神の前に何も隠す必要のない裸の状態でいることが必要なのである。
神が人間に選ぶ自由を与えたのは、人間が善悪を自分の基準で判断し、神のようになることを願っていたわけではない。神は、人間が自ら神を選び、神に依存する生き方を求めていたのである。しかし、人間は、神に背を向け、自らが神になることを選択した。
人間と神との関係はもはや以前のような100%の信頼関係ではなくなった。しかし、それでも神は人間への愛を注ぎ続け、いつか『彼』が人間を救いに地上にやってくることを約束された。
そして、実際にその『彼』は、イエスという名で現在から約2000年前のベツレヘムに生まれた。全く罪のない神の御子であるイエス・キリストが人としてこの世界にお生まれになり、私たちのために十字架の上でかわりに裁かれて、罪過のいけにえとなった。
そして、人間はそのキリストを信じる信仰によって、神に罪赦され、神との交わりを回復し、天に御国を相続することができると約束してくださった。
感想
私は、本書を振り返った時、神の大きすぎる一方的な愛を感じた。
神は、人間が生きるために世界を用意された。また、人間を神のかたちに似せて「非常に良い」存在として造り、人格と選択の自由を与えた。そして、人間に神の代表者として世界を管理する使命を与えた。さらには、人間が蛇の誘惑に負け、一方的に神に背を向けたにもかかわず、神はひとり子であるイエスキリストを犠牲にして、人間を救いに導いた。ついには、いつかイエスキリストが再び来られる時、世界は新しくされ、人間は神を心から喜び、神とともに歩むことできるようになる。
これほど、人間を愛している神は他にいるだろうか、と思わされた。
本書の範囲である1章1節~3章20節(天地創造、人の堕落、救いの預言)は、神の人間への愛の大きさを十二分に受け取ることのできる箇所である。そしてその神の愛の大きさを遠藤嘉信先生は余すことなく、本書で語っている。
多様化している現代を生きる私にとって、本書は一人一人の尊厳と生きる目的を確認させてくれた。また、計り知れない神の愛をもって造られ、生かされていることを確認させてくれ、自らの人生と賜物を用いて、神のために生きていきたい、という思いを与えてくれた。
全てが、人を愛するために造られた。そこは、人にとって良きもので満ちていた。すべてが良かった。それは、神にとって良かったとともに、私たちにとって、非常に良かったのである。